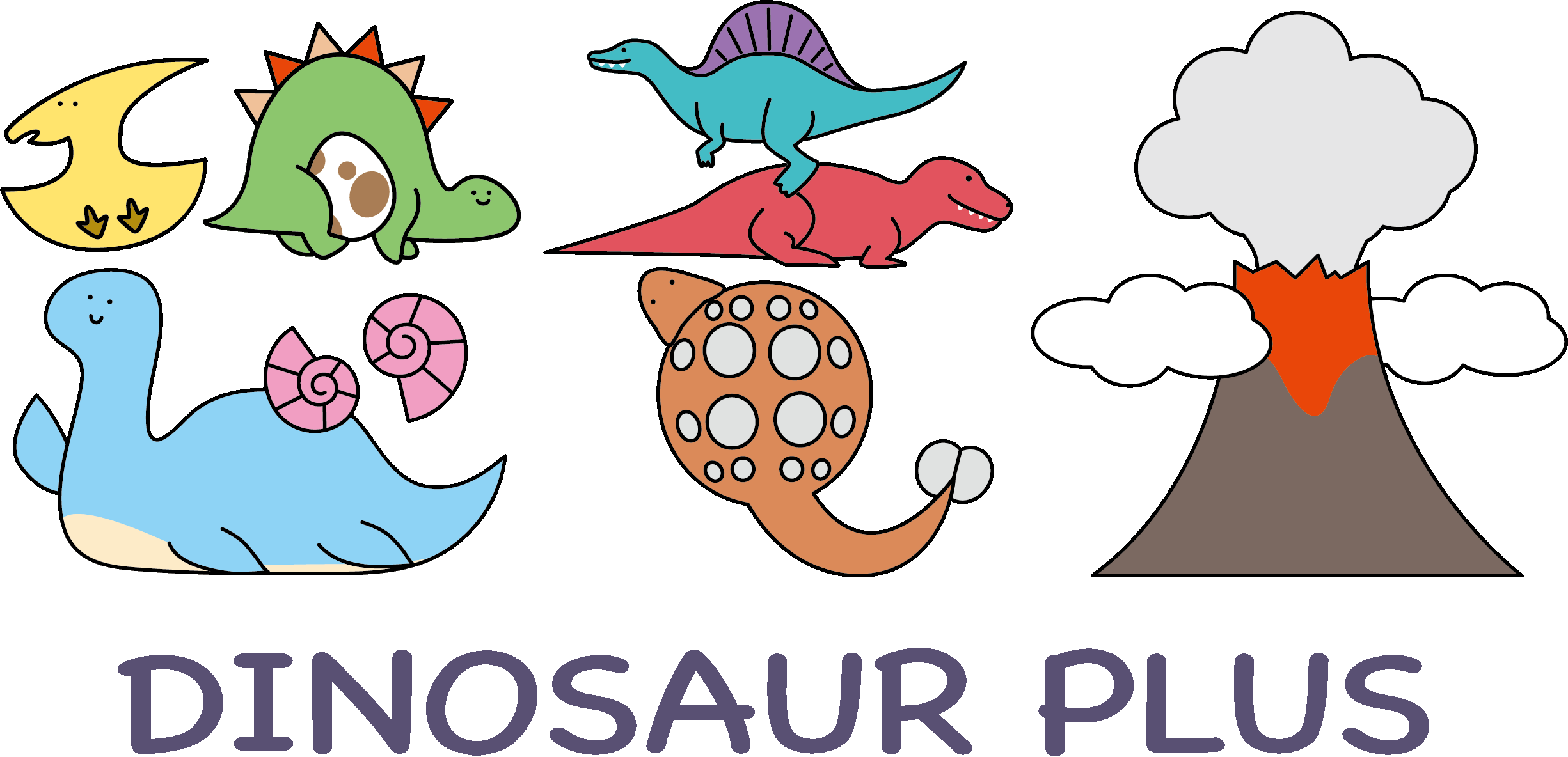目指せ恐竜博士to be a dinosaur doctor
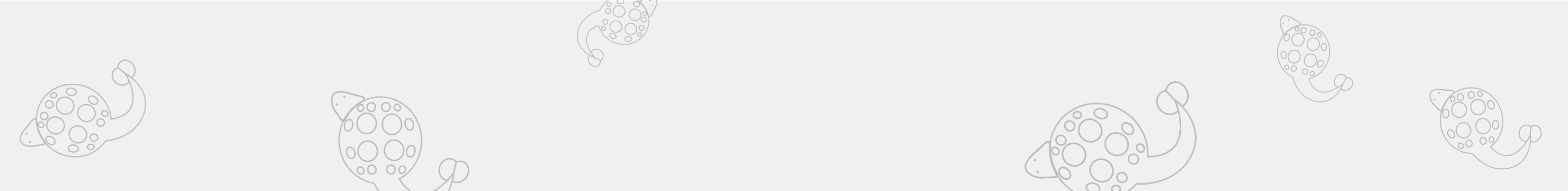


恐竜学者|吉田純輝博士にインタビュー(福島県立博物館 学芸員)
このコーナーでは、恐竜に関わる様々なお仕事の側面を紹介することを目的に、第一線で眩しく輝いている方々のインタビューをお届けしています。
恐竜の謎を解き明かす研究者たちは、どのようにしてその道を歩んできたのでしょうか? そして、恐竜研究の魅力とは何なのでしょうか?今回は、福島県立博物館の学芸員であり、恐竜の 「のどの骨」 に関する最新研究の論文なども発表されている 吉田純輝(よしだ じゅんき)先生 にお話を伺いました。
吉田先生は、日本国内の大学と大学院を卒業し現在も国内で研究を続けている、日本で注目されている若手研究者の一人です。
恐竜学者を目指す子どもたちに、このインタビューをぜひ読んでいただけたらと思います。恐竜研究の世界をのぞいてみましょう。
最初に現在のお仕事と、研究分野を教えてください。
福島県会津若松市にある「福島県立博物館」の古生物担当 学芸員として所属しています。
普段は福島県内での化石発掘・研究をはじめ、モンゴルをはじめとした海外へ調査に行くこともあります。
実は福島県では世界的にレアな時代「コニアシアン期(後期白亜紀の中頃8980万年前〜8570万年前)」の地層が見つかっています。この時代の地層は、日本では福島県と岩手県、北海道、海外では米国ニューメキシコなどに限られています。
中国やモンゴルでも白亜紀の地層はたくさん見つかっていますが、それがコニアシアン期かどうか正確にわかっている地層はありません。後期白亜期の中頃の地層は、世界的にまだわからないことが多いです。
コニアシアン期の地層に注目している理由は、この前後では恐竜の種類が違うことがわかっているからです。
例えばコニアシアン期の前は小型のティラノサウルスの種類が多いですが、その後の時代は大型に進化しています。
福島県ではこの地層から恐竜の化石が発見されていますが、まだ本格的な研究はされていません。そこで、そこで、まだまだ未知の発見がたくさん眠っているという期待に駆られながら、積極的に研究に取り組んでいます。
古生物学者になるために、学生時代はどのような勉強や研究をされていましたか?
私は恐竜や古生物の勉強をしようと思い、北海道大学の小林快次先生(※)の研究室で学びました。同じ研究室の先輩たちは、国際的にも古生物学者として活躍されている方が多いです。
私は子どもの頃から恐竜や古生物に興味があり、東京育ちだったので国立科学博物館にもよく行っていました。そんな中で国立科学博物館の真鍋先生とも何度かお会いしていて、高校生の時に将来の進路について相談をしました。そこで紹介していただいたのが北海道大学の小林先生です。
また、北海道大学では博士課程の時にニューヨークに研究留学をし、「アメリカ自然史博物館」で半年間の研究をしました。研究留学はとても苦労しましたが、この時にたくさんの出会いがあり、研究者としての考え方をかなり鍛えられたと思います。
ここでは「恐竜の舌の骨の研究」を自身の研究テーマとして取り組んでいました。
というのもかつてモンゴルから恐竜の舌の骨の報告があり、2015年にはアメリカ自然史博物館のマーク・ノレル先生のチームからも報告がありました。
これに似た骨が鳥類にもあり(舌骨)、現生の鳥類と比較することで恐竜がどのように舌を使っていたかわかるのではないかという研究プロジェクトを考えました。
※小林快次先生・・・北海道大学総合博物館の教授であり、同館副館長も務める古生物・恐竜学者。ゴビ砂漠やアラスカ、カナダなど海外での発掘・調査を精力的に行い、国内ではカムイサウルスをはじめとする新種の恐竜を多数発見。世界の恐竜研究の最前線で活躍されています。
ユニークなテーマですね!その研究でどんなことがわかりましたか?ワクワクした瞬間なども教えてください。
この恐竜の舌の骨の化石と、100種類以上の鳥の舌骨を見比べましたが、残念ながらどの鳥にも似ていませんでした。当初の計画としては大失敗でした。
ところが偶然博物館で目に留まった骨が、恐竜の舌の骨にそっくりだったんです。それは鳥の喉の骨でした。
そこで「自分が調べているのは舌の骨ではなく喉の骨なのではないか?」とインスピレーションが沸き、それをきっかけに研究の方針を大転換。「これは喉の骨かもしれない」と気づいた瞬間は興奮しましたし、大きな衝撃がありましたね。さらにたくさんの爬虫類・鳥類で喉の骨を見るたびに「これは喉の骨だ」と確信へ近づいていきました。2023年に「世界初発見!恐竜の喉の骨」として論文の発表に至りました。
古生物の研究においては、これまでに見つかったり研究されたりしているものを見ていても、まだまだ新しいものが見つかります。そして新しい発見を1つすると、新たにわからないことが10個くらい見つかり、新しい疑問がどんどん沸いてくるので、研究が進むのがとても面白いです。
一方で、研究者によって、何を見るか、どこに注目するかなど研究テーマが変わると思います。研究者それぞれの感覚に依存しているところもあるかもしれません。特に恐竜や古生物は今生きている動物と骨の形が違う部分もたくさんあるので、何に注目して見たらいいのかわからないこともあります。
だから恐竜研究には観察や着眼点、発想力がとても大事です。
子どもの頃から古生物が好きだったということですが、どんな子どもでしたか?
子どものころから古生物に興味がありましたが、ごく普通の子どもだったと思います。
また中学生のときは運動部だったので、恐竜だけに夢中だったわけではありません。中学3年生くらいから真剣に将来の進路を考えはじめ、古生物学者の道を目指すようになりました。
初めて自分で見つけた化石は何ですか?
初めて自分で見つけた化石は、貝化石(新生代のホタテのような貝)です。私の父が北海道出身ということもあり、道内の化石がよく産出する場所に連れて行ってもらったことがありました。
初めて恐竜の化石を見つけたのは大学生の時です。アメリカに行った際に、ユタ州立大学 イースタン先史博物館のケネス・カーペンター先生と一緒に東ユタに調査に行きました。その時には恐竜の上腕骨を見つけましたが、残念ながら周辺の骨は見つけることができませんでした。
これまでで特に印象に残っている恐竜展示はありますか?
アメリカ ペンシルバニア州のカーネギー自然史博物館での展示スタイルも面白かったです。「当時はこう生きていたかな?」と想像が膨らむような、環境再現にも力を入れたジオラマのような展示でした。日本であまりないスタイルであったことも印象的だった理由のひとつだと思います。
また、自然なポージングでディスプレイされていたのが印象的でした。1体1体の恐竜が「こんなストーリーがあったのでは?こんな世界で生きていたのでは?」など想像が楽しくなり、より一層恐竜の世界に入り込むことができた体験でした。
最後に、恐竜や化石の仕事を目指す子どもたちに、メッセージをお願いします。
古生物の勉強はもちろん重要ですが、先ほども言ったように、古生物学者は誰もわからない、気づいていないことを発見しなくてはなりません。新しいことに気づいたり、挑戦する姿勢や能力など、いわゆる非認知能力も大切だと思います。
まず、学校での勉強は頑張るとして、そのほかにもいろいろなことに挑戦してみてほしいですね。
また発掘調査で少し険しい場所(山や砂漠など)に行ったりすることもありますから、研究者には体力も必要だと思います。
私たち研究者も、かつては恐竜が好きな子どもでした。私がかつて古生物学者の先生たちの背を追いかけたように、今の子どもたちの中から、未来の恐竜研究者が生まれ、さらに次の世代へと恐竜好きが育っていくでしょう。そんなつながりのなかで恐竜の新発見がどんどんなされています。
君の「好き」が、どんな未来へとつながっていくのか楽しみにしています。